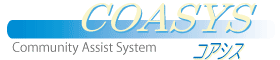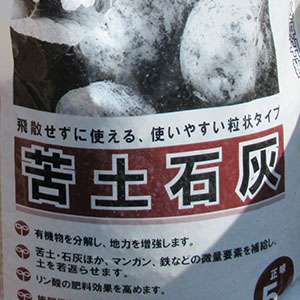栽培アドバイザー– pt_archive –
-

ピーマンの作付計画
ピーマンは、露地栽培では5月頃植え付け、6月から10月末頃までと長い期間収穫を楽しむことができます。 育苗期間は、比較的高い温度が必要で、育苗期間も長いことからまだ寒い季節に種をまく必要があり、種から育苗する場合には育苗器などの加温できる... -

コンパニオンプランツを植えることで病害虫抑制や成長促進が期待できる
コンパニオンプランツとは 異なる野菜を一緒に植えることで、両方、あるいは片方の害虫の抑制や病気予防、生長促進が期待できる、相性の良い組合せの関係にある植物を、コンパニオンプランツと言います。 これらの多くは、先人たちの永年の経験の積み重ね... -

イチゴの休眠と冬季の栽培管理
秋になって日が短くなり、低温になる11月頃、葉が小さくなりわい化し(新葉が徐々に小さくなり、地面にへばりついたロゼット状になる)、休眠に入ります。 秋から冬にかけて光合成による生産物は根に転流し、根量が増加してデンプンが蓄えられます。春の... -

タマネギの収穫
中晩生種は7~8割倒れたら収穫 一般的なタマネギは、5月中旬~6月上旬頃、球が大きくなって、全体の株の7~8割が倒伏したら、それが収穫の合図です。 タマネギは、球が肥大するとともに、葉の数も増やしますが、収穫時期を迎えると、生長が弱まって... -

酸性土壌に弱いため、石灰で中和
日本の土壌の多くは酸性に傾きやすいため、酸性土壌を嫌う野菜はそのままではうまく育ちません。 種まきの前に土壌のpHを測定し、野菜の品目ごとの好適pHになるよう、適量の石灰を散布して中和します。 pHの数値を1上げるには、苦土石灰なら100g/m²程度... -

ジャガイモの植え付け:基本は芽が上、裏技の逆さ植え
浴光催芽 種イモは、植え付け前に、20~30日間、日当たりが良く、雨などで濡れない場所で、日光にあて発芽させると、丈夫な芽が育ちます。 光がなるべく均等にあたるように、途中で2~3回位置を変えて、催芽むらをなくすようにします。 浴光催芽をするこ... -

弱酸性を好むため、土づくりに石灰は不要
多くの野菜栽培で、酸性に傾いた土壌を中和するために、野菜を栽培する前に石灰を撒くと思いますが、弱酸性を好む、あるいは強い野菜ですので、土づくりにおいて石灰を撒く必要はありません。 ただし、非常に強い酸性になっている可能性も否定できませんの... -

ソラマメはアブラムシが大敵
ソラマメの大敵はアブラムシです。 年内では、10月~12月にかけて温度が高く雨が少ない年に発生しますので、育苗時や生育初期にアブラムシの飛来防止をすることが大切です。 春になり暖かくなる4月~5月は、特に多くのアブラムシが発生しやすくなります。 ... -

又根ダイコンを防ぐ その原因と対策
大根の又根とは ダイコン栽培のよくある失敗の1つに、ダイコンが二又になるなど、又根ダイコンになってしまうことがあります。 たまに農家の庭先直売所にあったりもしますが、普通は売り物にはなりません。 別に売るためのものでなければ、十分食べること... -

発芽までは乾燥させない
ニンジンの種は乾燥に非常に弱い ニンジンは発芽させるのが難しい野菜の1つです。その種は保水力が無く、乾燥に非常に弱いためです。 1度吸水した種が、その後乾燥すると、発芽不良を起こします。種まきから発芽までの7日間から10日間、雨が降らない...
1